先週の国連気候サミット COP27 に約 200 か国が参加した際、日本はあまり知られていない変化を発表し、世界の気候外交、エネルギー、気候変動の舞台裏で何が起こっているのかを明らかにしました。 大した宣伝もなく、東京は国有の天然資源会社のブランド名を、地元企業が海外の石油、ガス、鉱業プロジェクトに投資するのを支援し、日本金属エネルギー安全機構に変更した. .
取るに足らない名前の変更のように思えるかもしれませんが、これは多くの国、特にアジアにとって重要な優先事項です。 エネルギー安全保障は最優先事項です。
また、日本がそのような目標を主導することも重要です。東京は 2023 年に G7 諸国の議長国となり、世界的なアジェンダを形作るための強力な説教台を日本に与えます。 日本はまだ G7 の優先事項を発表していませんが、アジアの外交官はエネルギー安全保障が優先事項になると言っているのを耳にします。
天然資源の世界では、政策立案者は長い間、原油から小麦、アルミニウムに至る商品について、供給の安全を確保し、価格を低く抑え、環境を保護する方法というトリレンマに取り組んできました。 このようなトリレンマは、多くの場合、3 つのうちの 1 つが他の 2 つに取って代わられることを意味します。
1970 年代と 1980 年代には、第 1 次と第 2 次の石油危機の記憶が新たにあり、供給の安定性と手頃な価格が持続可能性を打ち負かしました。 たとえば、1979 年の G7 諸国は年次サミットで、エネルギー コストを削減するために「可能な限り石炭の使用を増やす」ことを約束しました。 トリレンマのバランスは、現代の環境運動の台頭に伴い、1990 年代初頭に変化し始めました。 過去 10 年間で、地球温暖化の証拠が増えるにつれて、気候変動が優先事項になりました。
現在のエネルギー危機により、各国政府は優先事項の再考を迫られています。 安全性とアクセシビリティが戻ってきました。 確かに、政策立案者は、気候変動との戦いで後退していないと主張しています。 しかし、環境がもはや絶対的な優先事項ではないことは明らかです。 せいぜい、それは同等の中で最初です。 最悪、二の次です。
日本の経済産業大臣である西村康稔氏のアドバイスを受けてください。経済産業省は、その頭字語 METI で知られる非常に強力な機関です。 「各国は、安定したエネルギー供給を確保しながらカーボンニュートラルを達成するという目標を共有しています」と彼は先週、シンガポールで開催されたブルームバーグニューエコノミーフォーラム会議で説明しました。 彼が気候変動とエネルギー安全保障を同じレベルに置いていることに注目してください。
安全保障が新たに強調されたことが、COP27 が気候変動との戦いで本当に重要なこと、つまり化石燃料の消費と温室効果ガスの排出を削減する必要性についてほとんど進展しなかった主な理由の 1 つです。 豊かな国々は、気候変動による損失を貧しい人々に支払うための第一歩を踏み出しましたが、サミットは他にほとんど何もしませんでした. 欧州連合は、目標がさらに後退するのを避けるために、撤退すると脅迫しなければなりませんでした。
多くの点で、これは驚くべきことではありません。 エネルギー危機が気候変動との闘いを狂わせることはないという主張にもかかわらず、各国政府が優先事項を再考しないわけにはいきません。 OECD クラブの最も裕福な国でさえ苦しんでいます。 OECD の計算によると、今年は国内総生産の 17.7% をエネルギーに費やすことになり、これは史上 2 番目に高く、第 2 次オイル ショック時の 1980 ~ 1981 年の 17.8% にほぼ匹敵します。
エネルギー危機
GDP の % としての OECD 諸国の推定エネルギー消費支出
幸いなことに、今日のエネルギーのトリレンマは、G7 の政策立案者が 1979 年に東京でのサミットで皮肉にも解決策として石炭に目を向けたときほど困難ではありません。 それから 40 年が経ち、再生可能エネルギーは地球を保護し、セキュリティを向上させることができます。
ウラジーミル・プーチンが今年、ヨーロッパに対してガス供給を兵器化したときに示したように、化石燃料はグリーン エネルギーほど優れたセキュリティを提供しません。 G7 は風力発電と太陽光発電の拡大を推し進め、サプライ チェーンを改善し、研究開発費を増やし、プロジェクトの承認を早める必要があります。 家、ソーラーパネルが目標のはずです。 原子力は、環境と安全を両立する優れたツールでもあります。
エネルギーのトリレンマを解決するために日本ができる最大の貢献は、需要の削減に注力することです。 最良のエネルギー源は、消費されないものです。
過去に、政策立案者は、需要が増加し続けているにもかかわらず、供給を制限することによって気候変動に対処しようと誤って試みてきました. その結果、世界経済は新たな石油とガスの供給への投資が不足しており、価格は本来あるべきよりも高いままになる可能性があります。 解決策は、需要を減らすように、そして迅速に取り組むことです。
もちろん、言うは易く行うは難しです。 今のところ、化石燃料の需要は高まっており、石油、ガス、石炭は 2023 年に新たな消費記録を打ち立てる可能性が高いです。それが事実である限り、世界は間違った方向に向かっていることになります。
しかし、日本は別の方法があることを示すことができます。 1979 年には、1 日あたり 550 万バレルの原油を消費しました。 今年は 340 万ドルしか要求されません。 これはトリレンマの解決に向けた一歩ですが、暖房から運転まですべてを電動化するには、莫大で費用のかかる取り組みが必要になります。 G7 は再び増加する必要があります。
ハビエル・ブラスはエネルギーと商品を扱うブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。 ブルームバーグ ニュースの元記者であり、フィナンシャル タイムズのコモディティ エディターでもある彼は、『The World for Sale: Money, Power and the Traders Who Barter the Earth’s Resources』の共著者です。 @ハビエルブラス
免責事項: この記事は最初にブルームバーグに掲載され、特別シンジケーション契約によって公開されました。
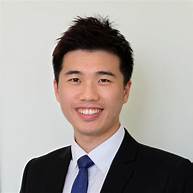
「Webオタク。テレビ中毒。ポップカルチャー愛好家。起業家。ベーコン忍者。受賞歴のあるインターネットオタク。」






