
トヨタ自動車の佐藤幸治社長は、東京で開催されたジャパンモビリティショーでEV「FT-Se」を初公開した。
2023年11月11日午前8時(日本時間)
多くのアナリストは、日本の自動車産業は国際的に高い競争力を持っているものの、電気自動車の競争で追いつく必要があると指摘している。 日本の自動車産業、特にトヨタ自動車は競争に勝ち残ることができるだろうか。 この質問を 3 つの異なる要素の観点から考えてみましょう。
1 つ目の視点は、電気自動車、特にバッテリー式電気自動車 (BEV) の販売の成長速度です。 BEVの販売は予想を上回る成長を見せた時期があったが、最近では米国、中国、欧州で減速している。 フォルクスワーゲンやフォードモーターなど世界大手企業は生産計画を下方修正した。
電気自動車世界最大手のテスラ社の株価が急落した。 一方、トヨタは好調な決算を発表し、ハイブリッド車の販売好調で市場の株価も切り上げた。
社会学者エベレット・ロジャーズが 1962 年の画期的な著書『イノベーションの拡散』で提案したイノベーション理論に沿って考えると役立つかもしれません。 彼の理論では、新しい製品やサービスをどれだけ早く、または簡単に採用するかに基づいて、人々を 5 つのカテゴリーに分類します。 最初の最小のグループは「イノベーター」で、人口の約 2.5%、次に「アーリーアダプター」(13.5%)、「アーリーマジョリティ」(34%)、「レイトマジョリティ」(34%)、最後に「後発者」(16%)。
自動車産業調査会社マークラインズによると、2022年には中国の新車販売台数に占める電気自動車(特にBEV)の割合は約19%、欧州では約11%、米国では約6%となっている。 日本では、この数字はわずか 1% 強でした。
したがって、電気自動車が比較的普及しているヨーロッパは導入の初期段階にあり、米国はやや遅れています。 電気自動車の普及が進む中国では、最初のユーザーの段階から最初の多数派の段階に移行しつつある。
アーリーアダプターはトレンドに敏感で、常にアンテナを張って情報収集と意思決定をし、新製品が大好きです。 一方で、最初の多数派は情報には比較的敏感ですが、新しい製品やサービスの採用にも慎重です。
自動車メーカーは、電気自動車を早期に多数派に普及させるために、製品をさらなる革新レベルに引き上げる必要があります。 新しいレベルのイノベーションには、自動運転機能やより高度なエンターテイメント オプションが含まれます。 低・中所得の消費者が車両を入手しやすくするために、価格を下げることも必要だ。 全固体電池は車両の航続距離を大幅に延長し、状況を一変させる可能性があります。
この段階での技術革新と投資決定が将来の成長を大きく左右します。
多くの専門家は、トヨタは電気自動車の導入に慎重すぎると主張している。 現在、トヨタは電気自動車の販売が最近の停滞を乗り越えて再び増加することを期待して、電気自動車戦略を加速させている。
世界最大の自動車メーカーであるトヨタは、世界中で年間約1,000万台の車両を製造・販売しており、2026年までに150万台の電気自動車を生産できる体制を構築する計画だ。電気自動車の販売が低迷する中、トヨタは10月31日に次のような発表を行った。米国の電池工場に追加で80億ドルを投資することも注目すべき動きだ。
問題は、電気自動車の重要なコンポーネントであるバッテリーが急速な技術革新にさらされており、すぐに老朽化して置き去りの資産になる可能性があることです。
自動車メーカーは適切なタイミングで投資判断を下す必要があります。 電気自動車の普及が鈍化するにつれ、投資のタイミングと種類が将来の競争を決定する上で重要になります。
3つの視点のうち2つ目は、脱炭素化を推進するための最適解の探索です。
単にガソリンエンジンの内燃機関車を電気自動車に置き換えるだけではなく、さらに多くのことを行う必要があります。
電気自動車は走行時にCO2を排出しません。 しかし、製造プロセスと電力消費量を考慮すると、電気自動車は排出ガスを出さないわけではありません。
トヨタによれば、2020年の地域別のエネルギーミックスを見ると、欧州では再生可能エネルギーが普及しているにもかかわらず、CO2を排出する火力発電がエネルギーミックスの38%を占めていたという。 日本では熱エネルギーの割合は 72% でした。 北米では56%。 中国では67%。 全世界では 65%。
このエネルギー源構成に基づき、製造プロセスやその他の考慮事項について一定の仮定を置くと、電気自動車からの CO2 排出量は 10 年間で 1 台あたり 28 トンとなり、ガソリン車の 34 トンよりも少なくなります。 一方、ハイブリッド車の排出量は電気自動車と同じ 28 トンで、プラグインハイブリッド車の排出量は 24.5 トンで最も少ないです。
発電分野の脱炭素化が進む中、発電分野の更なる脱炭素化が不可欠です。 エネルギー部門の革命により、電気自動車からの CO2 排出量は大幅に削減されます。
ロシアのウクライナ侵略によりエネルギー供給が制限され、エネルギー価格が上昇する中、脱炭素化の取り組みも障害に直面している。 エネルギー危機は、最初のポイントであるEVの普及速度にも影響を与えるだろう。
脱炭素化は短期的な視点だけではなく、2050年頃まで見据える必要があります。
そのとき、脱炭素社会の実現に向けて、発電分野では水素技術が重要な要素となる。
水素時代が本格化すると、電気自動車は脱炭素化においてより効果的な役割を果たすことになります。 水素を使用する電気燃料電池自動車は、特に実用車において普及する可能性があります。 水素燃焼エンジン車もオプションとなる。
技術の進歩は一枚岩ではありません。 何が主流のテクノロジーになるかは、予測できない改善の複雑なプロセスによって決定される可能性があります。 トヨタは「複線化」戦略の一環として、さまざまな技術開発を推進している。 トヨタ自動車の佐藤幸治社長は、読売新聞のインタビューで、各地域の顧客特性に合わせた最適なソリューションの組み合わせを提供し、エネルギー安全保障を確保することに重点を置く複線化戦略が現実的な選択肢であると述べた。 移行プロセスは現実的であり、消費者に受け入れられるものでなければなりません。
3 番目の視点は、経済とエネルギーの安全保障です。
日米欧の主要先進国において、自動車産業は多くの人材を雇用しており、各国の政治と深く関わっています。
電気自動車では中国メーカーが先行しているが、米国や欧州への輸出が大幅に増えれば政治摩擦は避けられない。
米国はインフレ抑制法を通じて中国製電気自動車を事実上排除してきた。 米中対立を踏まえ、米国は今後もさまざまな規制を通じて中国車の市場参入を阻止していくだろう。
電気自動車で自動車覇権を目指す欧州でも中国車の輸出攻勢にさらされており、中国メーカーが不当な補助金を受けていないか調査が始まるなど緊張が高まっている。
日本の自動車業界は10月28日から11月5日まで東京でジャパン・モビリティショーを開催し、電気自動車販売世界第2位の中国BYDが日本での販売攻勢を計画しており、初めて出展した。 。 しかし、日本のユーザーは国産製品に対する信頼が高いので、同社の戦略が成功するかどうかはまだ不透明だと思います。
政治的摩擦が深まれば、米国、欧州、日本、中国といった主要市場の間で、経済やエネルギー安全保障を巡って分裂が深まる可能性がある。
この傾向が強まるにつれ、先進国の自動車メーカーがコスト競争力のある中国製電池材料を採用することはますます困難になるだろう。 したがって、電気自動車の価格は下がらず、電気自動車の普及速度の鈍化という最初の見通しについての懸念が再び生じます。
長期的には、電気自動車への移行は続くでしょう。
しかし、現在の電気自動車の競争環境は不透明な段階に入り、深い霧が立ち込め始めている。 これら 3 つの要素が相互作用して電気自動車がどれだけ早く普及するかを決定しますが、複雑さは増大しています。 トヨタといえども、一瞬でも一歩間違えれば、自動車業界のトップから滑り落ちる危険がある。
「Political Pulse」は毎週土曜日に放送されます。

岡田章大
岡田章裕は読売新聞のコラムニスト。
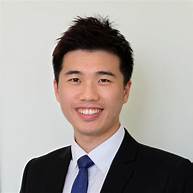
「Webオタク。テレビ中毒。ポップカルチャー愛好家。起業家。ベーコン忍者。受賞歴のあるインターネットオタク。」






