米国は日曜日、同盟国軍との連携を深めるため日本の軍事指揮を再編すると発表し、両国は中国をこの地域が直面する「最大の戦略的課題」と呼んでいる。
この発表は、アントニー・ブリンケン米国務長官とロイド・オースティン国防長官、そしてそれぞれの日本の対応者である上川陽子氏と木原実氏との間で東京で行われた安全保障に関する協議に続いて行われた。
「2+2」会談後に発表された声明によると、新たな「統合軍司令部」は日本軍とのさらなる相互運用性を促進し、3月までに軍隊を監督する統合司令部を設立するという日本政府自身の計画と並行して実施されることを目指している。
オースティン氏は交渉開始前に記者団に対し、日本における米国の指揮強化は「同盟の歴史の中で最も重要な進展の一つだ」と語った。
この見直しは、超大国中国から発せられるさまざまな脅威に言及し、各国が「進化する安全保障環境」と呼ぶものに対応するために講じられたいくつかの措置の一つである。
オースティン氏は「中国が東シナ海、南シナ海、台湾周辺、そして地域全体で強圧的な行動をとり、現状を変えようとしているのを引き続き見ている」と述べた。
声明は、中国政府の「挑発的な」海上行動、ロシアとの共同軍事演習、核兵器備蓄の急速な拡大などを批判した。
中国外務省はロイターのコメント要請に応じていない。
アメリカの核の傘
閣僚らは声明で「中国の外交政策は、他国を犠牲にして自国の利益となるように国際秩序を再構築しようとしている」と述べた。
「このような行動は同盟と国際社会全体にとって深刻な懸念であり、インド太平洋地域およびそれを超えた地域における最大の戦略的課題を表している。」
閣僚らは初めて、同盟国に対する攻撃を抑止するために核戦力を使用する米国の取り組みを表す「拡大抑止」についても議論した。
これは、核兵器の不拡散を主張し、唯一の原爆被爆国である日本にとってデリケートな問題である。
大まかな公式説明によると、両国は地域の安定を促進し、紛争の勃発を防ぐための拡大抑止力の強化について協議した。
「私たちは重大な岐路に立っています。 上川氏は交渉開始時に記者団に対し、「既存の国際秩序を完全に守るためには、同盟関係を継続的に強化し、抑止力、つまり力を向上させなければならない」と語った。
日本は米国にアジアでの軍事力を投影する基地を提供し、5万4000人の米兵、数百機の米軍航空機、そして唯一の前方配備空母群をワシントンに受け入れている。
中国の台頭と核兵器保有国である北朝鮮の定期的なミサイル実験の影響で、日本は近年、戦後数十年間の平和主義に比べて態度を根本的に変えている。 2022年には国防費を国内総生産(GDP)の2%に倍増する計画を明らかにした。
新たな在日米軍司令部は、日本が要求した4つ星将軍ではなく、3つ星将軍が率いることになると米当局者が会談前の記者会見で述べた。 プレスリリースではそれについては言及されていません。
韓国との協力
同盟国はまた、ロシアがウクライナ戦争を支援するために北朝鮮から弾道ミサイルを購入していることや、ロシアが大量破壊兵器やミサイル関連技術を平壌に移転する可能性に対して深い懸念を表明した。
北朝鮮は、戦争の際には敵を「完全に破壊する」と誓ったと国営北朝鮮通信社KCNAが日曜日に報じた。
オースティン氏と木原氏はまた、韓国のシン・ウォンシク国防相とも会談し、北朝鮮のミサイル警報データのリアルタイム共有や合同軍事演習などの取り組みを通じた3カ国の協力を「制度化」する協定に署名した。
バイデン政権は東京とソウルの協力深化を推進しているが、両国の緊張関係は1910年から1945年までの日本による朝鮮占領にまで遡る。
木原氏は三者会談後、記者団に対し、「この覚書は日米韓の協力を強化し、国際情勢がどう変化しても我々のパートナーシップは揺るぎないものとなる」と語った。
米国政府はまた、ウクライナと中東の紛争によって需要が圧迫されている米国の兵器製造業者に対する圧力を緩和するよう日本の産業界に求めたいと考えている。
日本とワシントンは、ミサイルの共同生産努力の推進、サプライチェーンの強靱性の強化、船舶や航空機の修理の促進など、この分野でのさまざまな協力を追求している。
しかし、主力プロジェクトであるパトリオット防空ミサイルの増産に日本の工場を活用する計画は、ボーイング社製の重要部品の不足により遅れているとロイター通信が今月報じた。
バイデン政権がますます大胆になる中国に対抗しようとする中、ブリンケン氏とオースティン氏は東京を離れた後、もう一つのアジアの同盟国であるフィリピンと安全保障協議を行う予定だ。
米国の会談記録によると、ブリンケン氏は土曜、ラオスで中国の王毅氏と会談し、米国とそのパートナー国が「自由で開かれたインド太平洋」の維持を望んでいることを繰り返した。
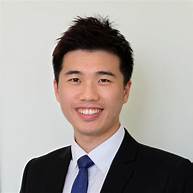
「Webオタク。テレビ中毒。ポップカルチャー愛好家。起業家。ベーコン忍者。受賞歴のあるインターネットオタク。」






