[東京 1月18日 ロイター] – 投資家市場が設定された限度を繰り返し超過する中、利回り調整政策は圧力の下できしむ音をたてており、中央銀行は利回り調整政策の運命を議論している。 1ヶ月前より。
日本銀行(BOJ)の政策が変更されれば、超緩和的な金融環境が短期的に終了するという市場の期待が高まり、円と長期金利の急激な上昇を引き起こす可能性があります。
しかし、日銀が政策変更を行わない場合、市場の反応はさらに大きくなる可能性があり、投資家は変化への期待に基づいて構築したポジションを急いで解消するようになります。
他の中央銀行は物価上昇に抵抗するために積極的に利上げを行っているが、日銀は長期金利をゼロ付近に維持しており、昨年の日本の異常なインフレに伴い消費と賃金の伸びを強めようとしている。
しかし、インフレ率が目標の 2% を上回っているため、日銀はイールドカーブ コントロール (YCC) と呼ばれる景気刺激策にとってこれまでで最大の試練に直面しています。
2016 年に導入された YCC は、短期金利を -0.1% に維持しますが、10 年国債の目標は 0% で、許容範囲はわずかです。
利回り上昇の圧力を受けて、中央銀行は先月、YCC の寿命を延ばすことを目的として、許容範囲を目標のプラスマイナス 0.5% 以内に倍増することで市場に衝撃を与えました。 したがって、10年債の上限は0.5%に上昇しました。
投資家がこれをさらなる利上げの前触れと見なしたため、この動きは裏目に出て、火曜日の市場で 3 日連続で最高値を更新する力強い債券の売りを引き起こしました。
一部の投資家は、中央銀行がキャップを守るために必要な大量の債券購入を維持できないと考えて、日銀が今週にも YCC の調整、または解体を余儀なくされることに賭けています。
SMBC日興証券のチーフ債券ストラテジスト、森田長太郎氏は「日銀の債券買い入れによる資金流出は異常な水準に達している。 「投資家や証券会社の観点からすると、日銀が現在の政策課題の維持をあきらめるかもしれないという感覚が強まっている.」
水曜日に終了する 2 日間の会議で、日銀は、YCC の事業を維持し、債券購入によって引き起こされた市場の歪みを解決するために、さらなる措置が必要かどうかを議論する可能性があります。
昇給待ち
金曜日に10年物利回りが上限の0.50%を超える前に、日銀の政策立案者は、4月に黒田東彦総裁の後継者が就任し、最近の賃金引き上げが全国的に定着した後にのみ、刺激策を段階的に廃止することを望んでいた、と情報筋はロイターに語った。
しかし、日銀がそれほど長く待つ余裕があるかどうかは不明です。
日銀は0.5%の利回り上限を強引に擁護して市場の歪みを是正する代わりに、市場の歪みを悪化させている、と批評家は言う。 早期の利上げに対する市場の期待は利回りを大幅に押し上げ、8 年物利回りは 10 年物利回りを上回った。
日銀のオプションを見て、一部のアナリストは、それがさらに幅を広げ、10 年物の利回りを 0.75% まで上昇させることに賭けています。 中央銀行が10年物利回りの目標を0%以上に引き上げるか、より短い満期を目標とするものに変更するか、または完全に放棄すると予想する人もいます。
日銀は行き詰まっている。 その他の表面的な調整は、金利が短期的に上昇するという市場の期待を単純に刺激する可能性があります。 しかし、利回り目標の引き上げまたは削除は、これまで主に輸入コストによって引き起こされてきたインフレ率の上昇に伴い、賃金の伸びが強まる前に YCC を修正または段階的に廃止することはできないという中央銀行のレトリックに反することになります。
一部のアナリストは、物価上昇の前向きな進展を見ており、インフレ率が上昇し、最終的に日本がデフレの考え方から脱却したときに、YCC は常に終了する運命にあったと指摘しています。
ロイターの元日銀エコノミスト、亀田誠策氏は「インフレが主にコストプッシュ要因によって引き起こされたのは事実だが、経済が好調だったために、企業がコスト上昇を消費者に転嫁できたのも事実だ」と語った。 「日本では前例のない変化です。」
水曜日に予定されている新しい四半期予測では、日銀はインフレ見通しを上方修正すると予想されている、と情報筋はロイターに語った。
日銀は、正午から午後 2 時 (03:00 ~ 05:00 GMT) の間のいつでも政策決定を発表する可能性が高く、その後、午後 3 時 30 分 (06:30 GMT) に黒田の記者会見が行われます。
木原れいかによるレポート。 ブラッドリー・ペレットによる編集
私たちの基準: トムソン・ロイターの信頼原則。
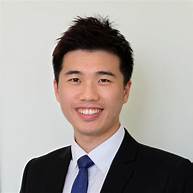
「Webオタク。テレビ中毒。ポップカルチャー愛好家。起業家。ベーコン忍者。受賞歴のあるインターネットオタク。」

/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/26ZFBPN7UFJ4HLJWPE4IBEFE5M.jpg)




