東京・四谷のビルのワンフロアに5教室を備えた大学キャンパスが6月にオープンした。
東京カレッジと呼ばれるこの教育機関は、中国のシリコンバレーとして知られる深セン市に拠点を置く深セン大学の初の海外分校です。
主な専門は中国語であり、教員は中国のメインキャンパスから派遣されています。 卒業すると、学生は中国のメインキャンパスの学生と同じ学士号を取得できます。
同大学の東京短期大学の第一期生はわずか5名だった。
高野秀一郎さん(24)も登録者の一人で、日本に居ながら中国語を学べる環境に惹かれた。
「私は中国に行ったこともなかったので、中国で勉強することは私にとって大きなハードルのように思えました。」と彼は言いました。
他の4人の学生は中国のルーツを持っています。
母親が福建省出身の紅いつみさん(22)は、中国のロールプレイングゲーム「原神」が好きだ。 彼女はビデオゲーム業界、特に日本と中国の橋渡しをする役割で働きたいと語った。
「私がこの大学に惹かれたのは、中国語を専攻するだけでなく、副専攻としてビジネスと情報技術を学ぶ機会があったことです」と彼女は言いました。
深センなどの中国の有名大学は日本に分校を設立し、世界トップクラスの成績と急成長する中国企業への就職支援で学生を惹きつけている。
これらの大学は、「日本にいながらにして有名大学の学士号を取得できる」教育機関を謳っています。 ただし、長期的な成功を収められるかどうかは不透明です。
東京短期大学では、3年次に半年間メインキャンパスで学ぶ機会があります。 中国語の基礎をマスターすれば、2~3年で卒業できます。
深セン大学は、アメリカの雑誌『ニュース・アンド・ワールド・リポート』により、日本の私立大学トップを上回り、世界第271位にランクされたことを誇ります。
また、IT大手テンセント・ホールディングスの日本法人への訪問やインターンシップなど、急成長する中国企業への就職支援も提供している。
初年度の授業料は122万円(8,200ドル)で、メインキャンパスで学ぶ留学生の約2倍です。
東京短期大学は来春に50人の学生を入学させる予定で、最終的には年間100人の入学を目指し、定員は400人となる。
日本企業との関係
2006年に神戸に開校した天津中医薬大学のキャンパスなど、日本では中医学を専門とする大学のキャンパスが誕生している。
近年、上海大学や済南大学などの総合大学が東京にキャンパスを開設し、中国語教育に力を入れています。
教育省は中国の4大学に外国大学の日本キャンパスを受け入れることを認定した。 中には数百人の生徒を受け入れたところもある。
深セン大学もこの指定を申請している。
東京カレッジは独自の資金で運営されます。 運営は森塾などの個別指導塾を運営する日本企業スプリックス株式会社と深セン大学が協力して運営しています。
森塾は中国でも運営していたが、中国政府の学習塾に対する規制強化を受けて2021年に撤退した。
日本でも少子化で需要の減少が見込まれる中、大学運営を通じて事業の多角化を目指す。
一帯一路イニシアチブの一環ですか?
北京語言大学東京学院は2015年に設立され、外国人向けの中国語教育を専門としています。
関係者によると、日本が管理し中国が領有権を主張している東シナ海の尖閣諸島を巡る領有権問題以降、中国への日本人留学生の数が減少しているという。
担当者は「日本で中国語を学びたい人の要望に応えたい」と話す。
近年、中国は特許取得や学術論文の出版において先行しており、世界的に重要な地位を占めている。 その大学は、さまざまな世界的な大学ランキングで常にアジアで最高のランクにランクされています。
現在約250名の学生が在籍する上海大学東京キャンパスの職員は、「日本に分校を設置すれば留学生数が増加し、母校の国際ランキングが向上する可能性がある」と語った。
中国教育省は2016年、国家構想「一帯一路」の沿線諸国に中国語教育を普及させる方針をまとめた文書を発表した。 中国と中央アジアおよびヨーロッパを陸と海で結ぶために10年前に開始された経済開発プログラム。
済南大学はウェブサイトに、「一帯一路」構想の海外キャンパス設立を担当するチームが東京からキャンパス設立に必要な事務作業を行っていると掲載した。
日本以外にも、ラオスの東州大学、マレーシアのアモイ大学、イタリアの同済大学や温州大学など、中国の大学も東南アジアやヨーロッパにキャンパスを開設している。
「分校の運営は中国の各大学に委ねられており、海外キャンパス設置の決定は各大学がビジネスチャンスと評価している。 しかし、それは中国政府の一帯一路構想とも一致している」と中国の高等教育に詳しい関西学院大学の非常勤講師で大学組織・経営の澤谷俊之氏は語った。
アメリカの大学は過去にも失敗している
中国の大学の拡大は、日本のパートナーにビジネスチャンスをもたらします。
中国語教育を専門とする4つの大学は、日本語学校運営会社によって運営されています。
日本語学校を卒業した留学生の中には、日本語学校と提携している大学の分校で中国語を勉強する人もいます。
東京北京語言大学の学生の約6割は日本人と中国人を除く外国人です。 同大学は、中国との関係を強化している東南アジア地域からの学生の間で需要が高いと述べた。
中国で表現の自由に対する制限が強化される中、日本は専門的な目的で中国語を学びたい学生にとって安全な環境であると考えられます。
しかし、これらの中国の大学の日本キャンパスが長期的に成功するかどうかは依然として不透明だ。
1990 年代、英語学習と海外留学プログラムの成長に直面して、約 30 のアメリカの大学が日本に設立されました。 しかしその後、多くの人がキャンパスを閉鎖したりオプトアウトしたりして、社会問題につながった。
これを受けて文科省は2005年、外国大学の日本キャンパスを認定する制度を創設した。
この制度は、日本の大学院への入学資格を付与し、日本の大学との単位互換を認めることで学生の不利益を防止することを目的としています。
「アメリカの大学は、学生が日本のメインキャンパスと同じ教育を受けられると宣伝していましたが、学生のほとんどが日本人であったため、その約束を果たす能力がありませんでした」と澤谷教授は語った。
「中国の大学キャンパスには、卒業生にメインキャンパスの卒業生と同じ雇用の機会を保障するなどの課題が待ち受けている」と同氏は述べた。
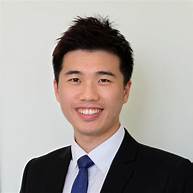
「Webオタク。テレビ中毒。ポップカルチャー愛好家。起業家。ベーコン忍者。受賞歴のあるインターネットオタク。」






