火曜日の安倍晋三の葬儀は、1967年の吉田茂の葬儀に続いて、日本の戦後史上2番目の元首相の国葬である.
吉田の国葬は、死後11日後の同年10月31日に執り行われた。 また、東京の日本武道館で行われ、テレビで生放送されました。
公葬記録によると、神奈川県大磯市の自宅から会場まで吉田さんの棺を運ぶ車列には、約17万人が参列した。 約 8,000 人の警備員が配備されています。
国葬には6000人以上が参列した。 当時の皇太子ご夫妻をはじめ、財界や各界の代表、72カ国の代表が参加。
式典の後、約45,000人の市民が献花に駆けつけたという。
報告によると、このプロセスには約 4 時間かかりました。
レポートには、イベントの準備段階で行われた討論の詳細が含まれています。 国葬の法的根拠については、法的な規定や制度上のルールがなく、さまざまな角度から賛否両論が検討されてきたと述べた。
届出書によると、同じく閣議決定に基づく昭和二十六年の大正天皇夫人の葬儀を例に、国葬は実質的に閣議の承認を得て行うことができるとの結論に達した。
内閣は、吉田氏の死から 3 日後に国葬を承認した。
当時、政府は各省庁に対し、葬儀当日に国旗を降ろし、1分間黙とうするよう要請した。
式典当日の午後は、官公庁にも休業や行事の自粛を要請した。 学校や民間企業にも同様の取り組みが求められています。
内閣府によると、吉田の国葬にかかった費用は合計で約 1800 万円、現在のレートで換算すると約 125,000 ドルです。 それは政府の準備金で完全に支払われました。
日本の国会の記録によると、国葬が終わった後、国会議員は国葬をめぐる法的な問題をすでに議論している。
記録によると、1968 年に野党議員が下院委員会で、国葬を行うかどうかを決定するには一連の基準が必要であると述べた。
当時の財務大臣は、準備金の支出の問題を解決するのに役立つため、一定の基準が必要であると個人的に考えていると答えた.
1969 年、当時の首相官邸の高官は、参議院の委員会で、一連の基準を将来的に検討する必要があると述べました。
しかし、1977 年、吉田氏の後継者は国会で、吉田氏の場合のように、今後の国葬は法律ではなく、閣議の承認に基づくべきであると述べた。
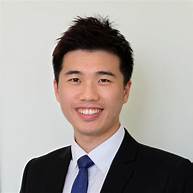
「Webオタク。テレビ中毒。ポップカルチャー愛好家。起業家。ベーコン忍者。受賞歴のあるインターネットオタク。」






